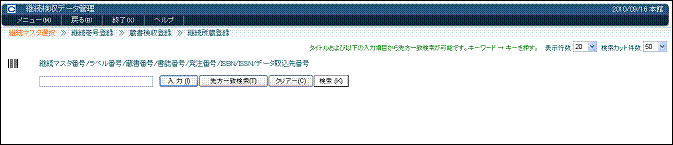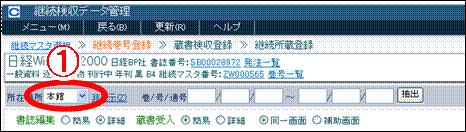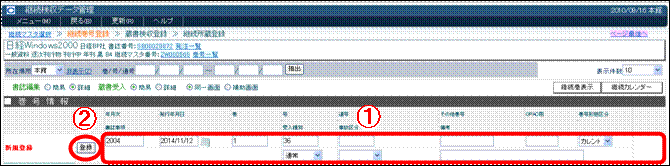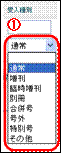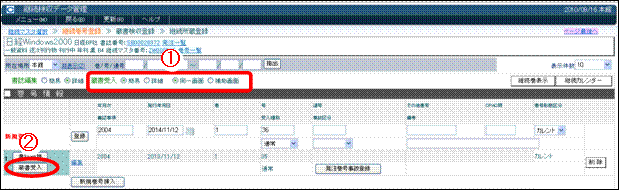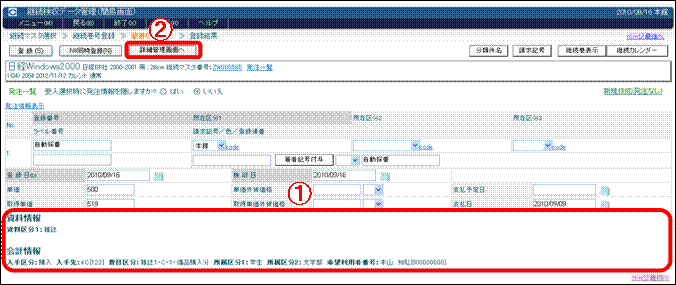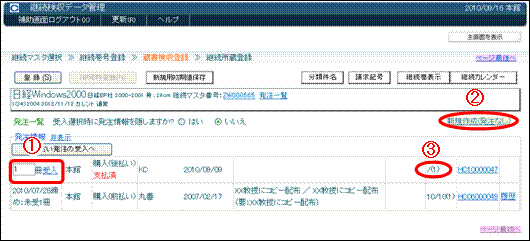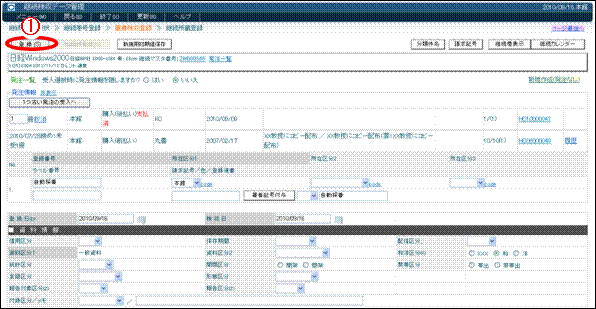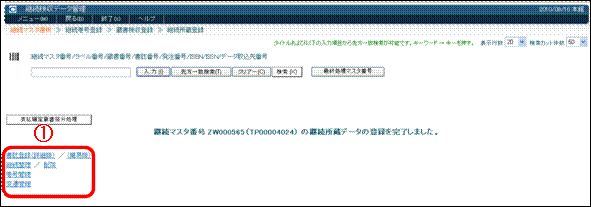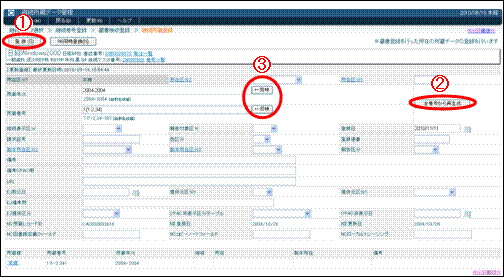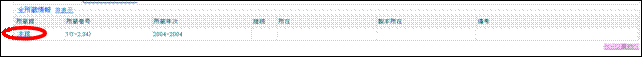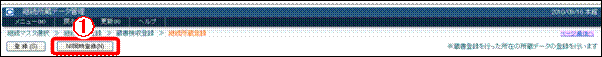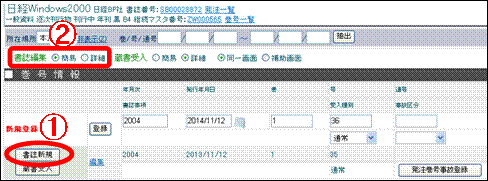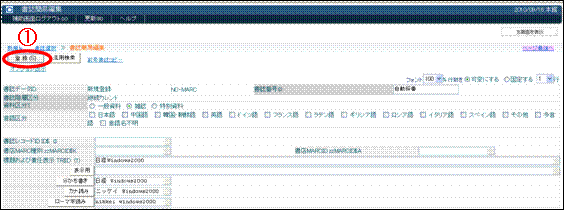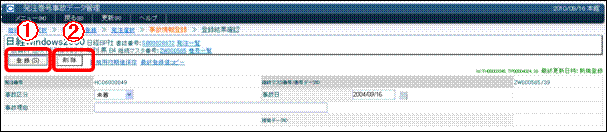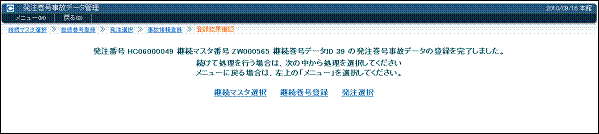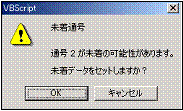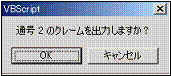継続資料を受入(検収・整理・配架)します。受入は発注分または未発注(寄贈など)から行います。
CARINでは資料の受入にあたる状態を、「検収」「整理」「配架」の3段階に分けて管理できます。
検収 → 資料が図書館に到着したことを確認した(検品した)状態
整理 → 資料にバーコードラベルや背ラベル等を装備した状態
配架 → 書架に配架した状態。貸出、閲覧できる状態
必ずしもこの3ステップを踏む必要はなく、配架1ステップのみで受入れる運用も可能です。
また、「検収」「整理」「配架」で行う作業手順は同じですが、「検収」処理を行い登録すると、その資料は「検収」状態に、「整理」処理を行えば「整理」状態になります。「配架」になるとこれ以上受入状態をすすめることはできません。
1.受入する継続資料を選択する
継続資料は、継続マスタ番号・書誌番号・発注番号いずれかを入力する(バーコードリーダーで読み取る)か、検索して選択します。また、タイトルから短縮キーを入力して選択することも可能です。選択方法は「はじめに」のページを参照してください。
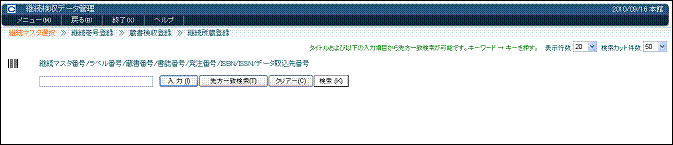
〈画面1 継続検収データ管理 継続マスタ選択〉
4.巻号を作成する
巻号情報を入力し、作成します。
☞ 入力フィールド〈画面4-①〉に必要事項を入力し、登録〈画面4-②〉をクリックしてください。
巻号形態区分は必須項目ですが、カレント・製本から選択できます。ここで製本を選択すると、製本資料を受け入れることになります(製本を束ねて受入れるのとは異なる)〈画面5左〉。
※ 増刊号や別冊の場合には、受入の際「受入種別」のプルダウンメニュー〈画面5右-①〉から種別を選択してください。
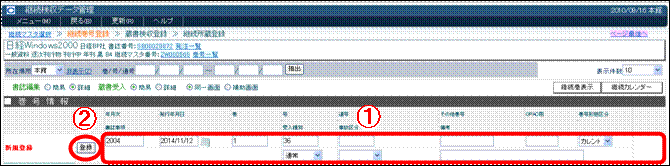
〈画面4 継続検収データ管理 継続巻号登録〉

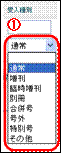
〈画面5 継続検収データ管理 継続巻号登録〉
5.カレントを受入する
☞ 蔵書受入を行う画面をラジオボタン〈画面6-①〉で指定して、蔵書受入〈画面6-②〉をクリックしてください。
受入画面には、詳細画面〈画面7〉と簡易画面〈画面8〉があります。最初の受入は詳細画面で行う必要がありますが、それ以降は初期値を引き継ぐことにより、簡易画面で受け入れることが可能になります。これらの画面は、補助画面でも開くことができます。同一マスタのカレントを複数受け入れる場合などにお使いください。
※ 子書誌を入力する場合は、「! 子書誌を登録する」を
事故を立てる場合は、「! 事故を立てる」を参照してください。
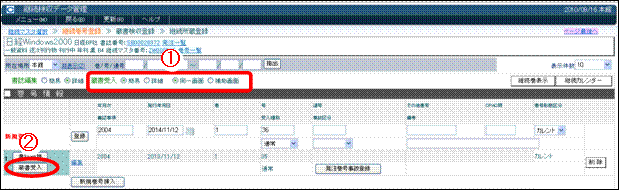
〈画面6 継続検収データ管理 継続巻号登録〉

〈画面7 継続検収データ管理 蔵書検収登録(詳細画面)〉
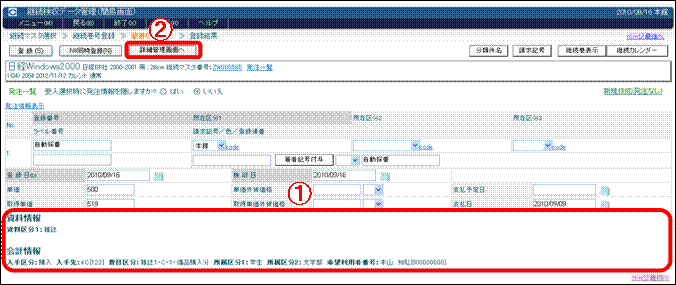
〈画面8 継続検収データ管理 蔵書検収登録(簡易画面)〉
! 蔵書受入簡易画面について
それぞれのカレントで異なる項目を除いて、登録する内容がサマリー〈画面8-①〉として表示されますので、登録と確認の手間が軽減されるようになりました。また、登録した内容から、所蔵年次、所蔵巻号を自動生成し、継続所蔵データの登録を行うようになっています。今まで通りの登録を行われる場合は、詳細管理画面ボタン〈画面8-②〉をクリックすることで、詳細管理画面に遷移することが可能となっています。
6.カレントの受入数を入力する
発注データの一覧が表示されます。すでに受入処理が行われている場合(受入冊数=複本冊数、事故区分あり、発注締日あり)はこの画面は表示されません。そのまま次のステップに進んでください。
☞ 受入する発注の「受入冊数」を入力し、受入をクリックしてください〈画面9-①〉。受入冊数は複本冊数が初期値となります。
発注が無い場合は新規作成(発注なし)〈画面9-②〉をクリックしてください。
※ 受入総冊数/受入予定巻数(複本冊数)も表示されています〈画面9-③〉。
(例:2冊の複本発注をした場合は受入冊数欄には「2」と表示されます)
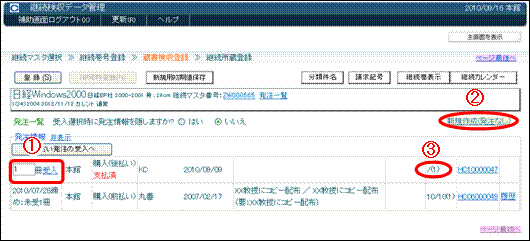
〈画面9 継続検収データ管理 蔵書検収登録〉
7.カレントの受入データを編集する
☞ 必要な項目を入力して、登録〈画面10-①〉をクリックしてください。
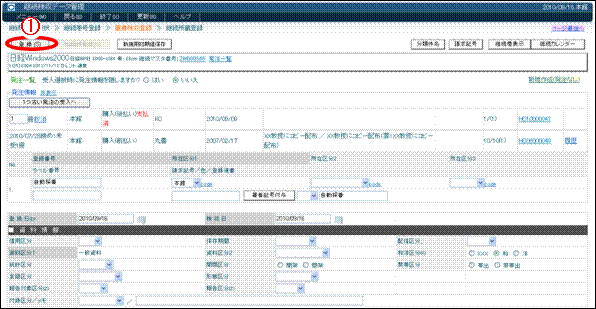
〈画面10 継続検収データ管理 蔵書検収登録〉
※ 登録完了後、画面1に遷移しますが、この際、続いて検収などを行いたい場合は、下記のリンク〈画面21-①〉をクリックしてください。
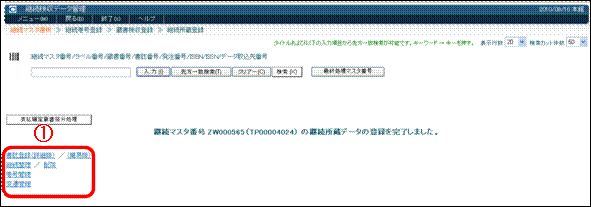
〈画面21 継続マスタデータ管理〉
! 各リンクの説明
|
リンク
|
内容
|
|
書誌登録(詳細版)/(簡易版)
|
新規に書誌を登録する場合に選択してください。
|
|
継続整理/配架
|
今回検収処理をした蔵書データの状態を整理もしくは配架にする場合に選択してください。
なお、対象となる蔵書データの状態が整理の場合は、配架のみ選択可能となり、配架の場合、リンクは表示されません。
|
|
巻号管理
|
今回検収処理をした継続マスタデータにリンクする場合に選択してください。
|
|
変遷管理
|
今回検収処理をした継続マスタデータに対応する書誌の変遷を編集する場合に選択してください。
|
! 各種日付について
日付により資料の状態が変わります。各種日付は自動で振られますが、任意に設定することもできます。
日付を削除すると、受入段階を戻すことができます(例:配架日を削除すると整理状態に戻る)。
! NII同時登録機能について
NII連携機能が有効になっている場合NII同時登録ボタンが表示されます。
NII同時登録ボタンをクリックすると、CARINへの蔵書の登録を行うと同時に、その情報を元にNIIへの図書所蔵登録を行います。詳しくは、「継続検収・整理・配架」の章の第8節に記述されている「NII同時登録機能について」の囲みをご参照ください。
8.所蔵情報を編集する
☞ 必要な項目を入力し、登録〈画面11-①〉をクリックしてください。
※ 「所蔵年次」と「所蔵巻号」は、全巻号からデータを生成することが可能です。
全巻号から再生成〈画面11-②〉をクリックして、←反映〈画面11-③〉をクリックしてください。
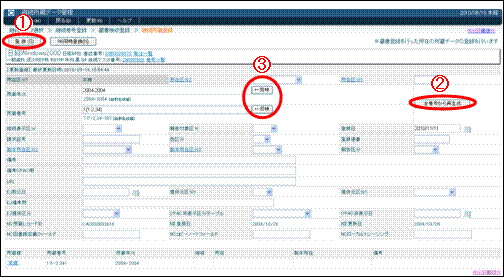
〈画面11 継続所蔵データ管理 継続所蔵登録〉
! 所蔵データについて
所蔵データは、どの図書館に、どの巻・号の、いつからいつまでのカレントまたは製本を所蔵しているかという情報を持ちます。これらの情報はNIIへの所蔵登録データともなります。
検索では継続資料の親書誌(相対的な表現。巻号が書誌を持つため、巻号は子書誌と呼ぶ)は、館とともに表示されます。
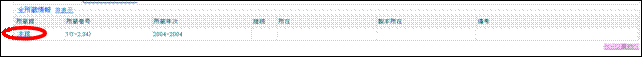
〈画面12 検索結果一覧〉
! NII同時登録機能について
NII連携機能が有効になっている場合NII同時登録ボタンが表示されます。〈画面22-①〉
NII同時登録ボタンをクリックすると、CARINへの継続所蔵の登録を行うと同時に、その情報を元にNIIへの雑誌所蔵登録を行います。CARINの継続所蔵情報からNIIへの所蔵登録への項目対応設定は、標準では次のようになっています(設定により変更可能です)。
・HLV = PHV
・HLYR = PHYR
・CONT = PCONT
・CLN = PHC1
・LDF = PNCLDF
・CPYNT = PNCCPYNT
・LTR = PNCLTR
NII同時登録ボタンは、次の条件に合致する場合はNII雑誌所蔵登録をすることができないため、グレーアウトしていてクリックできないようになります。
・リンクしている書誌データがNC MARCではない
・リンクしている書誌データにIDのタグが無い
・IDのタグに登録されている値が、NIIのSERIALデータベースに登録可能なフォーマットではない。
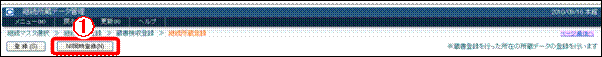
〈画面22 NII同時登録ボタン〉
(3) 事故登録を行う発注を選択します。事故登録を行う場合は「選択」ボタン〈画面17-①〉を押すことで、事故情報登録画面に移ります。また、「履歴」ボタン〈画面17-②〉を押すことにより、履歴が表示されます。

〈画面15 発注巻号事故データ管理 発注選択〉
(4) 事故情報を登録する画面です。事故区分は継続巻号登録画面で登録されている事故区分をデフォルトで表示します。事故日は、当日をデフォルトで表示します。「登録」ボタン〈画面18-①〉を押すことで、登録処理を実行します。なお、事故情報を解除する場合は、事故日・事故区分を空白にするか、「削除」ボタン〈画面18-②〉でデータを削除することで解除となります。
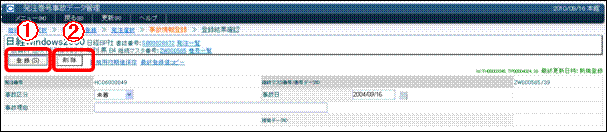
〈画面18 発注巻号事故データ管理 事故情報登録〉
(5) 登録結果の画面です。〈画面19〉のように表示されれば、正常に登録完了です。エラーが表示された場合は、前の画面に戻ってエラー内容にしたがって修正を行ってください。
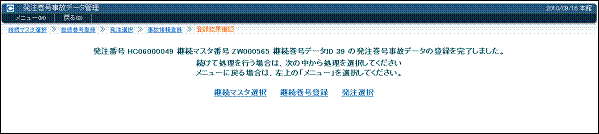
〈画面19 発注巻号事故データ管理 登録結果確認〉